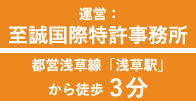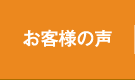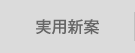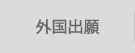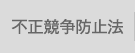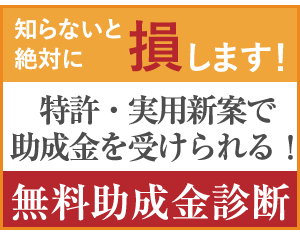「知財の創造サイクル」の実行
「知財の創造サイクル」とは一般に広く言われている
「知財の発掘 → 知的財産の権利化 → 権利の活用 → 知財の発掘」
という知財の循環サイクルのことを言います。
これを順を追って考えて行きます。
①「知財の発掘」
会社、企業の現場での技術に関するアイデア・ノウハウ(例えば、「こんな商品は今までなかった」「これは便利だ」)等は、基本的に知財として成立する可能性を多く含んでいます。
問題は、特許庁において保護される資格を持っているか否か、です。
この場合、知財として保護されるか否かの判断のポイントは、発明、実用新案に関しては、基本的には、そのアイデアによるメリット(利便性・効果)が大きいか、否かに係ります。
非常にメリット(効果)が大きい、という場合には、とりあえず、発明、考案として成立している可能性が高いといえます。
この次に、「調査」(抵触可能性調査・登録可能性調査)が必要となります。
意匠、商標は、そのようなデザイン、マークは今までにはなさそうだと思ったら、即時、「調査」(抵触可能性調査・登録可能性調査)が必要となります。
従って、アイデアは、即、出願を行う前に、先ず「調査」というフィルターでふるいにかける必要があります。
「抵触可能性調査」とは、他人の所有する知財権を侵害する可能性があるか否か、を判断することを目的とする調査であり、「登録可能性調査」とは、当該技術的なアイデア、デザイン、商標が、特許庁において権利として登録される可能性があるか否か、を判断することを目的とする調査です。
両者はオーバーラップする部分もありますが、観点が全く異なり、作業内容も異なります。
出願前にこの双方を行っておく必要があります。
現在では、IPDL(特許庁電子図書館)が非常に充実しており、誰でもパソコンでIPDLにアクセスして調査を行えます。
どなたもお気軽にやってみるといいと思います。但し、調査のツールを使いこなすにははやり非常な熟練が必要となります。
特許・実用新案でいえば、どのような観点で技術・アイデアを捉え、どのような分類(IPC)に落としこみ、どのような概念(Fターム、FIターム、キーワード)を使って実際に調査を行うか、は非常にデリケートな問題です。
ほんのわずかな分類の違いでも調査対象の世界が違ってしまい、調査結果には大きな相違がでてきてしまいます。
その意味で、調査はその後の全ての「知財活動」のスタートを決めるものであり、非常に繊細で「怖い」存在でもあります。
従って、特許事務所・弁理士側でも、非常に慎重に結論を出すこととなります。
調査において問題がなれば出願により「権利化」を目指すこととなります。
調査に関して質問があれば、お気軽にお電話下さい。
②「知的財産の権利化」
出願に当たっては、所定金額のお金をかけるものであり、当然のことながら「単なる権利化」ではなく徹底的に「使える権利化」を図ることが必要です。
そのためには以下の点が重要です。
ⅰ:特許
特許出願では、ともかく侵害訴訟となった場合に権利行使のベースとして
実際に使える明細書を作成することが重要です。
この場合の明細書作成側の感覚としては、「相手に勝つ明細書ではなく負けない明細書」を作ることとなります。
このような観点からは、「特許明細書」は、当然のことながら、「重層的な請求項」、「徹底した実施例記載」を行うこととなります。
明細書のページ数は増加し、ご請求書の「タイプ代」は少々、高くなりますが、何かあった時の保険代と思ってください。
審査においては、現状、出願審査請求から平均3年程度で最初の拒絶理由通知が発せられます。
特許庁の審査官の仕事は「特許をする」ことではなく、「拒絶をする」ことです。従って、現状、拒絶理由通知なしで特許となることはほとんどありません。
あくまでも、特許庁の審査官は、拒絶理由通知への出願人側の意見書・補正書による反論を勘案して特許の可否を決めます。
従って、調査を行っていた場合でも、なお、拒絶理由通知は発せられる可能性があります。
これは審査官の観点は常に拒絶を行うことにあり、証拠に少々の無理がある場合であっても拒絶理由通知を出してきます。
従って、この拒絶理由通知にいかに対応するか、が重要な問題となります。
より早期に結論を出す必要性がある場合には、「早期審査制度」を使用することにより概ね、3ヶ月で最初の通知を出してもらうことが可能です。
また、拒絶理由通知があった場合には、審査官との間でインタビューを行うことによりより効果的に出願人の意見を審査官に伝え、時間を節約して特許を成立させる可能性があります。
ⅱ: 実用新案(簡易・迅速な登録の確保)
実用新案の場合、方式審査のみが行われ、実体審査は行われることなく登録されます。
従って、新規性がなくとも(従来、同一のアイデアが存在したとしても)、出願から約2.5ヶ月で登録にはなります。
しかし、権利行使時には警告書に技術評価書の添付が義務付けられていることから、最低限、新規性は確保していることが必要です。
進歩性の評価は、ある面主観的な評価になりますから反論が可能ですが、新規性の有無は調査により明確かつ客観的に判別してしまうからです。
従って、実用新案の場合には「評価2」(進歩性の欠如)を確実に取るために出願前調査が必要となります。
従って、新規性を有することを最低限確保すれば、一応の権利主張ができる、という意味で実用新案登録の意義を有することとなります。
ⅲ:意匠登録
意匠はデザインであり、そのデザインと同一及び類似の範囲のみを保護するものであるため、権利範囲は特許、実用新案に比べると狭くなります。
では、意匠で保護することに意味がないか、といえばそうではなく、例えば、権利侵害の場面では、侵害品が登録意匠と同じか否か、が非常に分かりやすいことから、侵害か否か、の判断は、特許等に比して非常に容易となり、有効な保護が可能となります。
従って、物の形、模様等に特徴がある場合には、意匠登録で保護することが必要となりますが、うまく使えば、意匠登録は非常に有効な保護手段といえます。
但し、全体として、特許、商標に比して、意匠保護に関する社会的な認識はやや低く、意匠保護制度が十分に活用されている、とはいえません。
この場合、もし事情が許せば、一つの意匠につき複数件(3件程度)の関連意匠(類似するデザイン)の登録を確保することが、保護の観点からは非常に有効です。
ⅳ:商標登録
会社の営業を行う上で最も必要となるものが商標です。
会社の名称、商品の名称、サービスの名称を登録することが会社そのもの、営業そのものを守ることになりるため重要な登録となります。
商標の登録にあたっても、事前の調査が非常に重要です。
この場合も、他人の権利と抵触するか否かの「抵触可能性調査」と「登録可能性調査」の双方が必要となります。「登録可能性調査」に関しては、「抵触可能性調査」の場合よりも、詳細な調査が必要となります。
商標調査においては、特許の場合よりもさらに明確に、その後の審査のシナリオを描くことができます。
従って、商標調査は常に非常に重要な作業となります。
③「権利の活用」
ⅰ:紛争事件の有効活用
侵害の事実が分かった場合には、「警告書」を侵害者に送ることとなります。
が、警告書には、「侵害の停止、侵害品の廃棄、市場からの侵害品の撤廃」等を要求することと
なりますが、「警告書」の意味は、相手方に「侵害か否か」を真剣に考える
機会を与える点にあります。
送る側も送られた側もこの機会を利用して、もう一度、特許というものを、
経営全体の中でじっくり考えてみることが必要です。
特許はあくまでも経営のツールですので、経営環境の中で、特許の持つ意味をよく検討してその後の対応を考えることが必要です。
特許の最終的な意味は裁判所での権利の主張にありますが、権利者側は侵害者から多額の
金銭賠償を取れることを常に想定することは危険です。
知財訴訟での賠償額はさほど大きくなく、裁判等で要する費用との比較考量を常に検討する必要があります。
弁護士、弁理士に支払う費用が賠償額を上回ってしまったというようなこともありえますので、
注意が必要です。
ⅱ:訴訟立ち上げの意味
侵害者に警告書を送っても、訴訟提起前に双方合意に至ることはなかなか難しいものです。
侵害者側も事態を余り真剣に考えない場合もあります。
このような場合には、「訴訟」という環境の中で、裁判官という「行司」のいるところでお話しましょう、
ということになり、訴訟提起に至ります。
この場合には、侵害者側も必然的に真剣に対処せざるをえなくなり、紛争解決には有効に
寄与します。
しかし、あくまでも勝ち判決の獲得を目指すことよりも、
いかに有利な条件で和解をするか、を考えることをお勧めします。
実際、侵害訴訟を提起した場合、裁判所側はかなり早期から和解を提案してきます。
和解を行う場合の思考の出発点は、基本的に、相手方との「WIN-WIN」の関係の
成立にあります。
知財サイクルをお考えの方、お気軽にご相談下さい!
著者

所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。