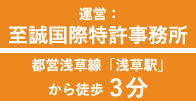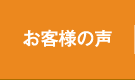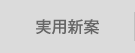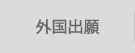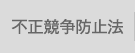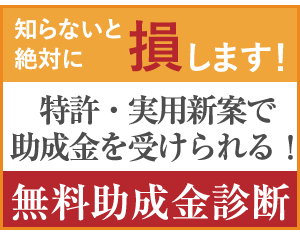初めて特許を取得する方へ −3つの条件をプロの弁理士が解説します−

1.特許を取得するための心得
特許は特許庁に申請(法的には「出願」と称します)することにより取得することができます。但し、簡単には特許を取得することはできません。
特許庁は「原則として特許はしません。但し、例外的にこれらの条件をクリアできれば特許を認めます」という体制になっております。従って、「特許は、特許庁と戦って勝ち取るもの」と思ってください。
即ち、特許されるために必要な条件が決まっており(「特許要件」といいます)、出願された発明が特許要件を充たすか否かを、事前に厳しく審査して、充たしていると特許庁が判断した出願のみを特許するようになっております。
ここが、行政手続としての「特許制」の厳しいところで、一定の条件が具備されていれば必ず認められる「許可制」(営業許可·道路工事許可等)とは大きく異なる点です。
では、特許要件、特許を取得するための手続、その実態、どのように準備すべきか、について以下にご紹介します。
2.特許取得の3つの条件(特許要件)
あなたが考えたアイデアが特許になるためには、おおかまに言って、以下の3つの条件を充たすことが必要です。特許庁の審査では、基本的には、出願された発明が、以下の3つの特許要件を充たしているか否か、を厳しく審査します。特許要件及び特許庁への手続に関しては「特許法」という法律に詳しく規定されています。
- ⅰ:発明の成立性(特許法第2条·特許法第29条柱書)
発明は「技術に関するアイデア」です。発明の種類としては、「物の発明」(~装置、~器具、~システム、~物質等)、「方法の発明」(~製造方法、使用方法)があります。
従って、「技術」に関するアイデアであることが必要であり、「(科学的な意味での)技術」を利用していない「人為的な取り決め」(ゲーム方法、遊戯方法、経済的取引方法、学習方法等)等は発明として認められません(特許法第2条)。
「技術に関するアイデア」の中には、技術的に非常に高度なもの(原子力利用の装置、自動車のエンジン、コンピュータの内部構造等)も、技術的には簡単な日用品も含まれます。但し、後者の場合には、特許を取ることにチャレンジすることもできますが、基本的には、実用新案套登録を取得されることをお勧めしております。この点は、「特許と実用新案との差異」で触れます。
特許を取得するためには、先ずは、この条件を充たす必要があります。これにより、特許庁と戦う土俵の上に乗ることができます。
- ⅱ:新規性(特許法第29条1項)
「発明成立性」をクリアし特許法上の「発明」であることが認められると、次に、実体的な要件の審査に入ります。これを「特許要件」と称します。特許要件の第一は「新規性」です。
「新規性」とは、「出願された発明が客観的に見て新しいか」という条件です。問題は「何を基準に、どの範囲で新しいか」と認定するか、が問題です。結論から言えば、「特許庁が所有刷るデータベースの特許情報の中に、出願された発明と同一の情報がなければ、『新しい』と認定」されます。従って、「新規性がある」とは「従来の発明等と異なる」ということです。
また、基本的には、マーケットにおいて同一の商品が存在しない、ことも最終的には勘案はされるのですが、先ずは、この環境の中で「新しい」と認定されることが必要です。
さらに、「新しい」ことは「国際的にみても新しい」ことが要求されます。これを講学上、「世界公知主義」と称します。従って、出願された発明は、日本のみならず、米国、中国等においても「新しい」ことが要求されますが、この点は、審査では、概ね、日本のデータベースの中において「新しい」ことが認定されれば、暫定的に「新しい」ものとして取り扱われます。
従って、「その発明が新規性を有しているか否か」は、特許庁のデータベース(「I-Platpat」と称します)に入り込み、サーチをすることによりアセスメントできます。この場合、「新しい」と言えるためには、「その発明と従来の発明等が完全に同一であるか否か」に関する認定なので、どこか少しでも異なる、という場合には、「新規性がある」という認定になります。
「新規性」の具備が認められると、次に、もう一つ難問の条件が待っています。「進歩性」です。
- ⅲ:進歩性(特許法第29条第2項)
「進歩性」とは、「新規性を有することを前提として、その発明が従来の技術から進歩していますか」という条件です。ここで問題は「進歩とは何か」ということです。上記の「新規」とは「従来の発明とは異なる」ということですが、「進歩」の概念はやや曖昧です。
要は、「新しい発明であっても、従来の発明等を参考にして簡単に作れるような発明には特許を認めません」という条件です。従って、「進歩性」とは、「その発明が簡単には作れなかった」ことです。
特許庁はなかなか、その発明に進歩性があることを認めません。ほとんど必ず、進歩性を否定する通知を出してきます。その場合には、反論ができますので、出願人は「進歩性がある」ことを主張、立証を行うことができます。
従って、出願人の特許取得における主戦場は、この「進歩性」の有無に関する戦いになります。多くの出願人の方が、この進歩性という特許要件をいかにクリアするか、で非常にご苦労されます。また、代理人としては「この発明は進歩性がある」ということを特許庁にいかに納得させるか、という点で実力が試されることになります。当然に、代理人·弁理士はこの点に関する様々なノウハウを持っております。
なお、進歩性も基準は「世界中の特許文献に基づきその発明を簡単に作れたか否か」が問われます。この点に関しても、出願する前に、特許庁のデータベースにアクセスして関連する特許出願の公報(公開公報)をサーチして関連する特許文献を抽出し、本件発明と対比することにより「その発明が進歩性を有している、と言えるか」に関するアセスメントを行うことができます。
進歩性の考え方
上記の通り、新規性は非常に客観的でクリアな概念なので、ある意味「ゼロ·イチ」の世界で、「新規性があるか、ないか」というシンプルな判断です。従って、新規性に関して「その発明が新規性があるか、否か」で問題になる、審査官との間で議論になることは稀です。
一方、進歩性は、本来的に流動的な概念であり、「日本国としてどのような発明を保護するか」に関する産業政策的な基準であり、判断主体、技術分野によってもハードルの高さは異なる、流動的な概念です。
また、「何が進歩性か」という点に関しても、議論があり、特許庁の中でも、審査における判断と、審判における判断が異なる場合あり、さらに、特許庁の考え方と裁判所の考え方が異なる場合もあり、また、各国特許庁における考え方が異なる場合もあります。
特許庁の審査についての考え方
そこで、どのように考えるべきか、というと、少なくとも、日本特許庁では、審査でも審判でも「その出願の発明の効果が、進歩性がないという証拠として上げられた引用文献に記載も示唆もない」ということの主張、立証が成立すれば基本的に進歩性は容認されます。
但し、上記のように進歩性は非常に微妙、かつやや流動的な概であることから、特許成立性の観点、侵害成立の有無の観点から、バトルフィールドとなることの多い、話題の多い特許要件です。
特許庁の審査では各特許出願の審査を各審査官が担当して、上記の「発明の成立性」、「新規性」、「進歩性」等に関する審査をします。審査官がいずれかの要件が欠けている、と判断した場合にはその旨の通知「(特許することを)拒絶(する)理由通知」を出願人(直接には代理人)宛に発送します。出願人側では代理人(弁理士)と打合せをして、審査官に対して反論ができます。代理人としてはここが腕の見せ所であり、「特許庁と書面をもって戦う場面」となります。
このような特許庁での「戦場」は、「審査段階」と「審判段階」に2段階構成で、言ってみれば、裁判所における「地裁」と「高裁」のようなものです。特許出願は、先ずは、審査段階に係属し審査官により審査され、特許を拒絶された場合にはそれに対して意見書、補正書を提出して反論をします。これで、審査官が反論に納得して特許になれば万々歳なのですが、場合によっては、最終的に拒絶され、審査段階では特許が容認されない場合もあります。
このような場合で、出願人として「まだチャレンジしたい」という場合には、費用と時間はかかりますが、もう一回、特許取得に向けてチャレンジすることができます。これが「審判」であり、審判請求をして、事件を審判に持ち上げ、再度、審査してもらうことができます。審査との相違点は、審査では一人の審査官が特許要件の審査を行いましたが、審判では3人のベテラン審査官が「審判官」となって、裁判所と同様に「合議体」を構成し、3人の合議で「特許要件」の審査を行います。
審判と審査の対比をした場合、審査では、どちらかといえば「画一的な判断」がされます。また、一人の審査官の審査ですから、どうしても、その担当した審査官の発明観、技術観、世界観に支配されます。従って、似たような案件でも担当した審査官により判断が異なる、ということも事実上ありえます。
より客観的な判断が期待できる審判
これに対し、審判では、3人の合議による判断が行われますから、より客観的な判断が期待できます。また、審判の場合には、特に、「審判官との面談」の効果が大きく、直接に審判官との口頭でのやり取りを行うことにより、非常に当該事案の個別事情を勘案してくれる場合があります。その結果、審判まで頑張った場合の特許化率は、当所経験では非常に高いものとなります。
また、審判でもなお特許が拒絶された場合には、知財高裁へ出訴して、特許庁を被告として裁判で争うこともできます。さらに、知財高裁の「原告敗訴」(特許できないという判断)判決に対して不服な場合には、最高裁へ出訴することもできます。
従って、特許の場合には、全体で、「特許庁·審査→審判→知財高裁→最高裁」と4段階で「特許取得」にチャレンジできるようになっております。
諦めない!審査で特許にならなければ審判で特許庁と戦う!
上記の解説のように、進歩性拒絶が審査で克服できず、審判に至ることもあります。日本の特許審査は「2審制」を採っており、審査で特許にならなくても、さらに、審判で特許庁と戦うことができます。
この場合、出願人が大企業の場合には、出願件数も非常にも多く、また、審判費用はさほど小さくないことから、審査で特許にならない場合に。審判でさらに争う場合はさほど多くはありません。
中小零細企業の場合には、もし、費用と時間が許すのであれば、ぜひ審判で戦うことをお勧めします。理由は、審判の場合には、審査とは特に、進歩性の考えかたが異なる場合、ハードルの高さが異なる場合があるからです。
審査における「進歩性」の考え方は非常に画一的で「特許審査基準」(特許光における審査の内規)に基づき一人の審査官によりほぼ機械的に行われます。
一方、審判においては、(審判官面談を行うことが望ましいのですが)、個別具体的な事情を勘案しつつ特許要件全体の判断を行います。従って、中小零細企業·個人にとっては、審判ではより有利な環境築くことができる可能性があります。
実用新案制度と特許制度の違い
中小零細企業の場合には、特許取得のみならず、常に、実用新案登録の取得も平行して考慮すべきです。以下に、実用新案制度と特許制度の相違点について説明します。
実用新案制度は「小発明」を保護する制度で、本質的には特許制度と変わりはありません。
即ち、実用新案制度において登録により保護される対象は特許と同様に「技術に関するアイデア」です。但し、実用新案登録により保護される対象が「物品の形態に関する技術的アイデア」に限定されていることから、「方法に関するアイデア」は実用新案では保護されません。
さらに、特許制度の場合には、「事前に特許要件を審査して特許すべきか否かを決定する」ものですが、実用新案制度の場合には「登録要件を充たしているか否かについては事前に審査せず、登録後に必要な場合にのみ審査する」という制度になっております。これを「無審査制度」と称します。
但し、「物品の形態に関する技術的アイデア」であれば、実用新案でも特許でも保護される可能性はあります。また、要求される条件も特許と同様に「新規性」及び「進歩性」であり、そのハードルの高さも変わりません。
従って、特許制度と実用新案制度の間には相互に乗り換え可能な手続が設けられております(出願変更)。また、相互に出願及び登録の情報が審査の際に参照されます。その結果、もし、「この発明は特許でチャレンジするには少々、進歩性のハードルを越えるので苦労する可能性があるな」という場合には、実用新案で登録することも考慮に入れることが有効です。
即ち、仮に「進歩性が要求されるハードルを越えていない可能性があるのではないか」という疑義がある場合には、特許出願によりチャレンジした場合、審査で進歩性の主張に苦労し、さらに、審判においても進歩性が認められず最終的特許にならない、という悲劇もありえます。このような事態を回避するためには、実用新案登録制度による保護をお勧めします。
即ち、実用新案登録制度は無審査制度であることから、仮に、進歩性が要求されるレベルに達していない、という場合であっても、実用新案登録になります。その結果、実用新案制度により登録をし、実用新案権を保持することにより、実質的にビジネスを守れる、ということもあります。
従って、特許による保護を求めるか、実用新案登録による保護を求めるか、について柔軟に検討すべき事項であります。なお、特許権と有効な実用新案登録(技術評価が6点の実用新案套億)に基づく実用新案権の抗力の強さは変わりません。従って、他人による模倣、権利侵害の事態に対しては、断固とした対応(警告、製造、販売の差止請求、損害賠償請求)が可能であり、保護の程度にも差異はありません。
当所も実用新案権に基づく侵害訴訟を代理したこともあり、その有効性に関しては、ほとんど、特許に劣ることはない、といえます。
著者

所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。
特許お役立ち情報の最新記事
- 中小企業知財について
- 中小企業知財と知財意識
- 中小企業知財と紛争事件2
- 中小企業知財と紛争事件2
- 中小企業知財と紛争事件1
- 補論:特許査定と判決文
- 中小企業知財と発明の進歩性4:具体事例
- 中小企業知財と発明の進歩性3:具体事例
- 中小企業知財と発明の進歩性2
- 中小企業知財と発明の進歩性1
- 大企業知財と中小零細企業知財
- 初めて商標登録をされる方へ−商標のマストな基礎知識−
- −プロの弁理士が解説!−特許侵害紛争事件について
- <特許取得事例>「革新的被服技術案件」
- <特許取得事例>「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例―
- <特許取得事例>「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―
- <特許取得事例>分割出願による特許ポートフォリオ―
- <特許取得事例>分割出願によらない特許ポートフォリオ―
- COVID-19と特許問題
- 国際段階を管轄するPCT制度
- 特許制度調和の歴史
- パリ条約とPCT
- 世界知的所有権機関(WIPO)と特許制度調和
- 世界の知的所有権の国連専門機関–WIPO–
- 特許要件・「進歩性」とは
- ★プロ弁理士が解説!日本の実用新案制度の紹介−自社のマーケットを守るために−
- 実用新案制度・中小企業には必須の制度
- PCT国際調査制度
- 特許審査について
- 事務所の実力が決まる!特許事務所の“パラリーガル”について
- 分割出願戦略・特許ポートフォリオ
- 実用新案制度(2)
- 特許審査と審判の関係
- 経験豊富な弁理士が解説-日本における「色彩(一色)のみの商標」の取扱-
- 弁護士と弁理士の関係
- 紛争事件と「記載要件」
- 中小零細企業と特許(知財)について
- 特許調査の概要・意義と特許調査のメリット
- 特許マップ(パテントマップ)の概要と意義
- 特許の請求の範囲と明細書の書き方
- 特許の無効審判とは?無効審判の意味と申請の流れ
- 特許出願・特許申請で必ず注意しなければならないポイント
- 特許にも有効期限・期間はある?申請時に意識しないといけないポイント
- 特許査定の概要と意義
- 特許申請の流れを教えてください!
- 特許年金とはいったい何?
- 特許の申請、どれくらい費用がかかるの?
- 特許の取り方の大まかな流れと注意するべきポイント
- 最新の特許法改正による影響は?
- 特許法の存在意義と必要なシーン
- 特許を扱うのに必要な資格とは
- 特許事務所の仕事と必要なスキル
- 特許翻訳の仕事と必要なスキル
- 特許庁と商標の関係
- 特許庁に採用されるために必要なこと
- 特許庁のお仕事と必要なスキル
- 特許に関わるお仕事の種類とは