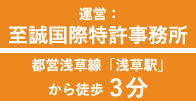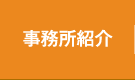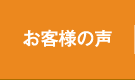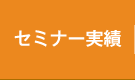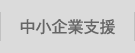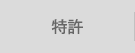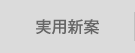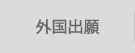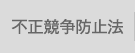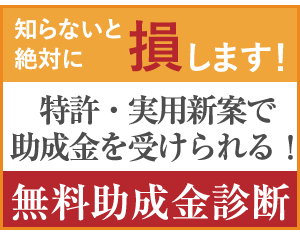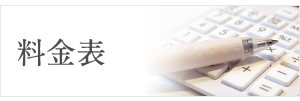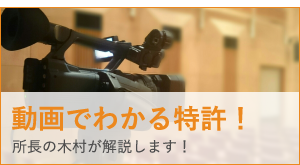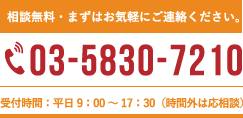特許を扱うのに必要な資格とは
特許査定とは?特許査定までの大まかな流れを解説。
特許査定とは特許庁の審査官が、出願された書類のチェックを始めとする審査を行い、一定の条件をクリアした申請に対して特許権を付与する決定をすることです。
特許権取得のための合格通知のようなものとも言えます。合格通知という表現をしたのは、査定を受け取ったのち30日以内に登録料を支払わなければ権利を行使する資格が発生しないからです。権利の取得まで少し複雑なので、最初から大まかな流れを辿ってみましょう。
まず、出願をするにあたって個人で書類を揃えることもできますが、作成した書類に不備があると余計に時間がかかりますので専門家に相談することをお勧めします。作成した書類を提出する前に、類似した技術がすでに特許権を取得していないか調査します。もしなければ申請書類を特許庁へ提出し書類のチェック(方式審査)を通れば、出願審査請求を行って実体審査を受ける資格を得ることができます。
ここで、拒絶査定か特許査定かが決まります。特許査定の獲得と権利の維持には費用がかかりますので、熟考の末出願審査請求をしないという選択も可能です。
特許査定までにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
景気の状態によって変動はありますが、例えば平成26年度では特許の出願数は32万件を超えています。それを2000名足らずの審査官が審査を行っていますので、特許権を取得するまでには2年前後かかると言われています。出願をしただけでは、内容の審査(実体審査)は行われませんので審査請求を出すわけですが、それを期限ぎりぎりの3年待って出せば更に長い年月がかかるわけです。3年を過ぎると実態審査を受ける資格が無くなります。審査が2段階になっているのは、申請者が特許権を獲得するメリットについてじっくり考えるための時間を設けているのです。
これは出願されたすべての案件のうち実際に特許査定を得られるのは2割に満たない現実を見れば、特許庁、申請者双方の便宜を図っているとも言えます。
特許という制度は何のためにあるのでしょうか。その意義は?
申請する側の立場でみれば、特許権を得ることで利益を得られるということが申請理由のうちでもっとも重視される点です。
一方、特許査定が降り登録された技術は広く社会に公開され産業の発展に貢献することになります。これがこの制度の意義と言えるでしょう。このため、査定が降りるための条件は厳しくなるのです。
例えば、実体審査の審査項目として、出願された技術が産業の発展に貢献するものであるか、誰でも再現可能なものであるか、今までに全く前例のないものであり創作性があるか、その分野でいち早く申請された最先端の新しい技術であるか、全く今までにない発想で創作されたものであるか、などが特許の資格があるかのかどうか厳しく審査されます。満たさない案件については拒絶査定の対象となり、申請者は補正書、意見書を提出し再度トライすることになります。
著者

所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。
特許お役立ち情報の最新記事
- 中小企業知財について
- 中小企業知財と知財意識
- 中小企業知財と紛争事件2
- 中小企業知財と紛争事件2
- 中小企業知財と紛争事件1
- 補論:特許査定と判決文
- 中小企業知財と発明の進歩性4:具体事例
- 中小企業知財と発明の進歩性3:具体事例
- 中小企業知財と発明の進歩性2
- 中小企業知財と発明の進歩性1
- 大企業知財と中小零細企業知財
- 初めて商標登録をされる方へ−商標のマストな基礎知識−
- −プロの弁理士が解説!−特許侵害紛争事件について
- <特許取得事例>「革新的被服技術案件」
- <特許取得事例>「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例―
- <特許取得事例>「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―
- <特許取得事例>分割出願による特許ポートフォリオ―
- <特許取得事例>分割出願によらない特許ポートフォリオ―
- 初めて特許を取得する方へ −3つの条件をプロの弁理士が解説します−
- COVID-19と特許問題
- 国際段階を管轄するPCT制度
- 特許制度調和の歴史
- パリ条約とPCT
- 世界知的所有権機関(WIPO)と特許制度調和
- 世界の知的所有権の国連専門機関–WIPO–
- 特許要件・「進歩性」とは
- ★プロ弁理士が解説!日本の実用新案制度の紹介−自社のマーケットを守るために−
- 実用新案制度・中小企業には必須の制度
- PCT国際調査制度
- 特許審査について
- 事務所の実力が決まる!特許事務所の“パラリーガル”について
- 分割出願戦略・特許ポートフォリオ
- 実用新案制度(2)
- 特許審査と審判の関係
- 経験豊富な弁理士が解説-日本における「色彩(一色)のみの商標」の取扱-
- 弁護士と弁理士の関係
- 紛争事件と「記載要件」
- 中小零細企業と特許(知財)について
- 特許調査の概要・意義と特許調査のメリット
- 特許マップ(パテントマップ)の概要と意義
- 特許の請求の範囲と明細書の書き方
- 特許の無効審判とは?無効審判の意味と申請の流れ
- 特許出願・特許申請で必ず注意しなければならないポイント
- 特許にも有効期限・期間はある?申請時に意識しないといけないポイント
- 特許査定の概要と意義
- 特許申請の流れを教えてください!
- 特許年金とはいったい何?
- 特許の申請、どれくらい費用がかかるの?
- 特許の取り方の大まかな流れと注意するべきポイント
- 最新の特許法改正による影響は?
- 特許法の存在意義と必要なシーン
- 特許事務所の仕事と必要なスキル
- 特許翻訳の仕事と必要なスキル
- 特許庁と商標の関係
- 特許庁に採用されるために必要なこと
- 特許庁のお仕事と必要なスキル
- 特許に関わるお仕事の種類とは