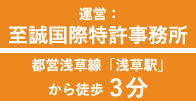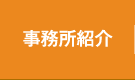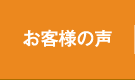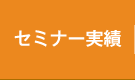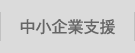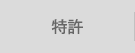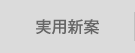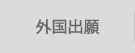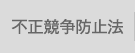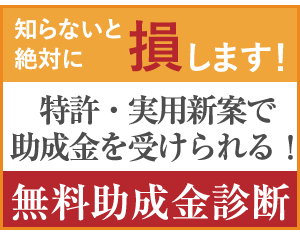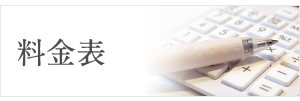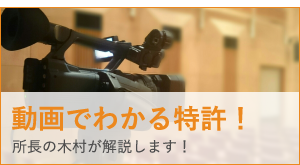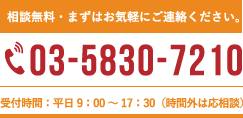中小企業知財と発明の進歩性2

中小企業の発明の特許性に関し、私個人の体験に基づきお話をさせていただいております。
大企業の発明の場合には、元々、圧倒的な技術力があることから、基本的に、特許審査においては大きな説得力があり、審査官を納得せしめるだけの課題と効果が明確であれば、進歩性(構成の困難性)を元々持っている場合が多いといえます。
一方、中小零細企業発明の場合には、非常に構成が簡易なものが多く、仮に課題と効果が従来技術に対して明確に成立していたとしても、構成が簡易な発明をいかに特許にするか、という点で、弁理士の技量がより試されまることになると思います。
即ち、確かに課題と効果は従来技術に比して明確なのですが、いかんせん構成が簡単、という場合に進歩性をいかにクリアするか、という問題です。お
例えば、私が経験した一つの事例は、一見、高さの低い直方体の弁当箱のような形の紙製の食品収納容器ですが、側面部が底面部から上端開口部に向かってわずかに開くように傾斜しております。この傾斜角度が85度というところが、ミソで一般の単なる食品収納容器とは異なる、という事例でした。
課題、効果は、「完全な直方体の場合には厚さ方向に入れ子状態では積み重ねられず、製造後、食品を詰め合わせる業者に輸送する際に、厚さ分だけそのまま積み上げなければならないため搬送スペースが嵩み、搬送効率が悪いが、側面部が85度の場合には、互いに入れ子状態で積み重ねられるため、多数の容器を効率よく厚さ方向に積み重なることができ、搬送の際のスペースを節約でき、多数の容器を搬送できるため、搬送効率が良くなる。試行錯誤の結果、85度という数値を見つけ出した」というもので、非常に立派な課題、効果が成立しております。
但し、この効果を奏する元となる構成は「側面部が85度で開口するように形成されている」ことのみです。この事案を受任した際に、依頼人は強気で「ぜひ特許を取得してほしい」
ということであったため、「果たしてこれで進歩性をクリアできるだろうか」と不安になった記憶があります。
この問題は、そのまま発明の進歩性の本質を「構成の困難性」を重視するのか、「効果の顕著性」を重視するのか、という問題につながって行きます。
特許庁の審査では、「効果の顕著性」は一つのメルクマールになりますが、やはり「構成の困難性」が進歩性の判断基準で、構成が簡易な場合には、一般的に、審査官はなかなか進歩性を容認しない傾向がある、ように思われます。
これは、特許法が、特許法第29条第2項において「従来技術に基づき容易に発明することができた時は特許を受けられない」と規定しているため、「容易に発明を構成出来たか否か」を進歩性判断のメルクマールとすることが自然であることに起因していると思われます。従って、特許庁の審査では「進歩性とは発明を構成することの困難性である」という思想が根強いのではないか、と思われます。
私見ですが、意見書で、進歩性拒絶に対する反論では、本願発明の効果が拒絶文献に記載されていない場合には「効果の顕著性」を主張しますが、必ず、「従って、本願発明には引用文献所載の発明に比して構成の困難性がある」という結論につなげることが重要と考えています。
裁判所では、発明の効果の「予測不可能な顕著性」を重視しているようですが、資金が潤沢ではない中小企業の場合にはは、審決取消訴訟で裁判所まで行く事態は、重要な侵害訴訟の場合をのぞき、ほとんどありません。また、知財高裁における覆審率が非常に低いことを考慮すれば、代理人の立場としても、「拒絶審決に対して知財高裁へ出訴しましょう」とは非常に進めにくい事情もあります。
従って、なんとか、特許庁の審査段階で決着をつけ、権利化する必要があるわけでですが、中小企業の「構成は簡単だが効果は大きい」という発明はどうしても不利になります。
特許お役立ち情報の最新記事
- 中小企業知財について
- 中小企業知財と知財意識
- 中小企業知財と紛争事件2
- 中小企業知財と紛争事件2
- 中小企業知財と紛争事件1
- 補論:特許査定と判決文
- 中小企業知財と発明の進歩性4:具体事例
- 中小企業知財と発明の進歩性3:具体事例
- 中小企業知財と発明の進歩性1
- 大企業知財と中小零細企業知財
- 初めて商標登録をされる方へ−商標のマストな基礎知識−
- −プロの弁理士が解説!−特許侵害紛争事件について
- <特許取得事例>「革新的被服技術案件」
- <特許取得事例>「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例―
- <特許取得事例>「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―
- <特許取得事例>分割出願による特許ポートフォリオ―
- <特許取得事例>分割出願によらない特許ポートフォリオ―
- 初めて特許を取得する方へ −3つの条件をプロの弁理士が解説します−
- COVID-19と特許問題
- 国際段階を管轄するPCT制度
- 特許制度調和の歴史
- パリ条約とPCT
- 世界知的所有権機関(WIPO)と特許制度調和
- 世界の知的所有権の国連専門機関–WIPO–
- 特許要件・「進歩性」とは
- ★プロ弁理士が解説!日本の実用新案制度の紹介−自社のマーケットを守るために−
- 実用新案制度・中小企業には必須の制度
- PCT国際調査制度
- 特許審査について
- 事務所の実力が決まる!特許事務所の“パラリーガル”について
- 分割出願戦略・特許ポートフォリオ
- 実用新案制度(2)
- 特許審査と審判の関係
- 経験豊富な弁理士が解説-日本における「色彩(一色)のみの商標」の取扱-
- 弁護士と弁理士の関係
- 紛争事件と「記載要件」
- 中小零細企業と特許(知財)について
- 特許調査の概要・意義と特許調査のメリット
- 特許マップ(パテントマップ)の概要と意義
- 特許の請求の範囲と明細書の書き方
- 特許の無効審判とは?無効審判の意味と申請の流れ
- 特許出願・特許申請で必ず注意しなければならないポイント
- 特許にも有効期限・期間はある?申請時に意識しないといけないポイント
- 特許査定の概要と意義
- 特許申請の流れを教えてください!
- 特許年金とはいったい何?
- 特許の申請、どれくらい費用がかかるの?
- 特許の取り方の大まかな流れと注意するべきポイント
- 最新の特許法改正による影響は?
- 特許法の存在意義と必要なシーン
- 特許を扱うのに必要な資格とは
- 特許事務所の仕事と必要なスキル
- 特許翻訳の仕事と必要なスキル
- 特許庁と商標の関係
- 特許庁に採用されるために必要なこと
- 特許庁のお仕事と必要なスキル
- 特許に関わるお仕事の種類とは